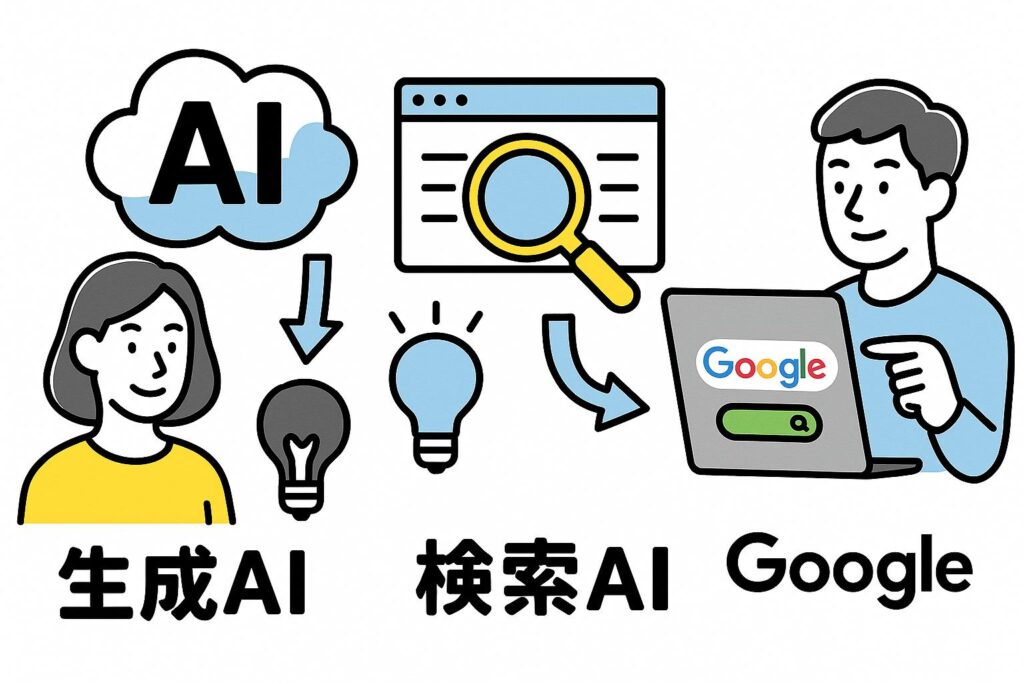
最近、AIの進化によって、私たちの「情報の探し方」が大きく変わってきています。
たとえば、Googleで「〇〇とは?」と検索していました。最近では、代わりにChatGPTなどのAIに「〇〇って何?詳しく教えて」と聞くと、すぐに答えが返ってくるので、まるで人と会話しているように情報が手に入るようになってきました。
こうした新しいスタイルの検索は「生成AI検索」と呼ばれ、これまでのキーワード入力型の検索と混在するように使われるようになってきています。
この記事では、「生成AI・検索AI・Google検索」の違いをわかりやすく整理しながら、目的に合わせた使い分けのコツを紹介していきます。
生成AIとは?

生成AIとは、AIが自分で文章や画像、音声などを作り出すことができる技術のことです。
たとえば、「ブログの記事を書いて」とお願いすると、AIが自然な文章を考えてくれたり、「会社のロゴを考えて」と頼むと、イメージ画像を作ってくれます。まるで、専属のクリエイターが横にいるような感覚です。
代表的な生成AIは、以下のようなものがあります:
- ChatGPT(チャットジーピーティー)
- Gemini(ジェミニ)
- Claude(クロード)
これらは「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれる、たくさんの文章を学習して賢くなったAIで、文章を生成することに特化していると考えて良いです。
詳細は下記サイトを参照してみてください。
検索AIとは?
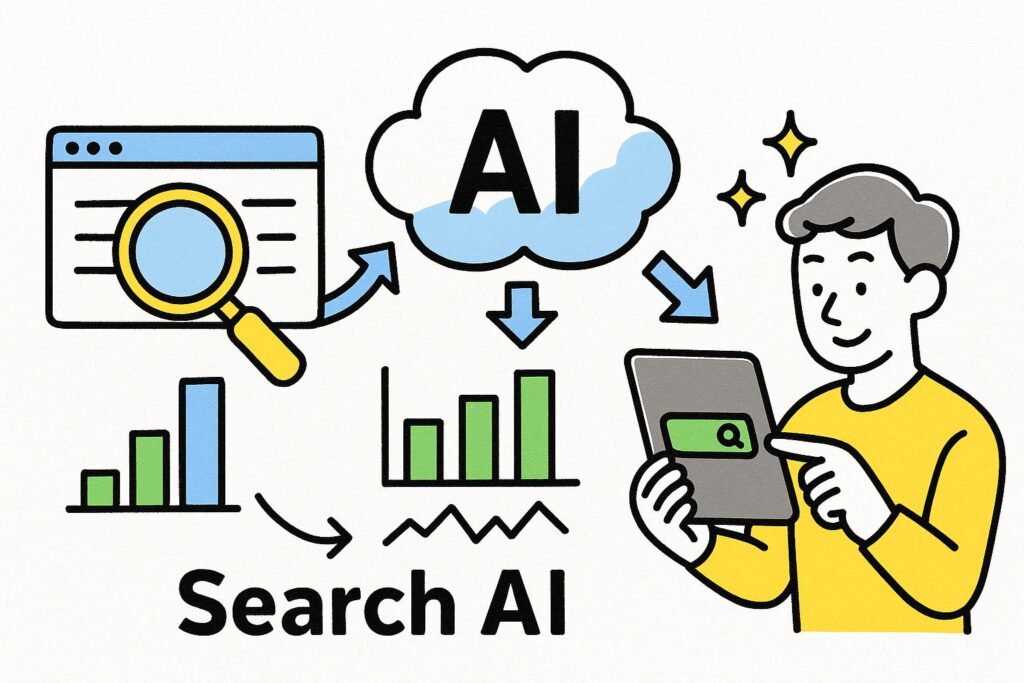
検索AIは、AIが質問の意図を読み取って、ぴったりの答えを返してくれます。
たとえば、「おすすめのチームコミュニケーションツール」と調べると、検索AIは「この人は業務効率化に使えるツールを探してるな」と判断して、それに合った答えと参考リンクをセットで表示してくれるのです。
代表的な生成AIは、以下のようなものがあります:
- Perplexity(パープレキシティ)
- Genspark(ジェンスパーク)
- Felo(フェロ)
どれも要約と根拠URLをセットで示してくれるツールなので、リサーチする場合などには非常に重宝するツールになっています。
生成AI・検索AI・Google検索の違いは?
これまでは、情報を調べたいときに 「Google検索」 を使うのが当たり前でした。しかし、近年では 「生成AI」 に質問して答えを得ようとする人も増えてきています。ただし、生成AIによる回答は厳密な「検索」とは言えません。
というのも、Google検索、生成AI、そして 「検索AI」 と呼ばれる新しいタイプのAIでは、答えの仕組みが大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴と違いをわかりやすく整理していきます。
Google検索
インターネット上にすでにある Webページを検索 し、入力したキーワードに合致しそうなページを人気や関連性に応じて並べて表示してくれます。
例えば「おすすめのカフェ 京都」と検索すれば、複数のサイトが一覧として表示され、自分で判断して目を通していく形式です。
情報源が比較的明確なので、信頼性が比較的高いというメリットがあります。
生成AI
過去に学習した大量のテキストデータをもとに、「この質問にはこう答えるのが妥当だろう」という推測・確率で文章を生成するのが、生成AIの特徴です。
ChatGPT、Claude、Geminiなどが該当します。
たとえば「京都でおすすめのカフェを教えて」と聞くと、AIは知っている知識を基にそれっぽい答えを構成します。しかし、
- 特定の情報源を参照していないので信頼度が曖昧
- 生成した情報が誤っている(ハルシネーション)可能性がある
- 出所不明で裏取りしにくい
といったリスクがあります
検索AI
ネット上の最新情報を リアルタイムに検索し、AIが回答の裏付けとなるWebページや引用を一緒に提示してくれます。
Perplexity AI、Felo、Gensparkなどが該当します。
このAI は、検索結果を要約しながら 参照した文献の元のリンクを明記してくれるという特長があります 。つまり、生成AIのように文章を作る力もありつつ、Google検索のように 正確な情報に基づく調査にも強い という両者の良さを併せ持った存在なのです。
どちらが優れている?使い分けのコツ
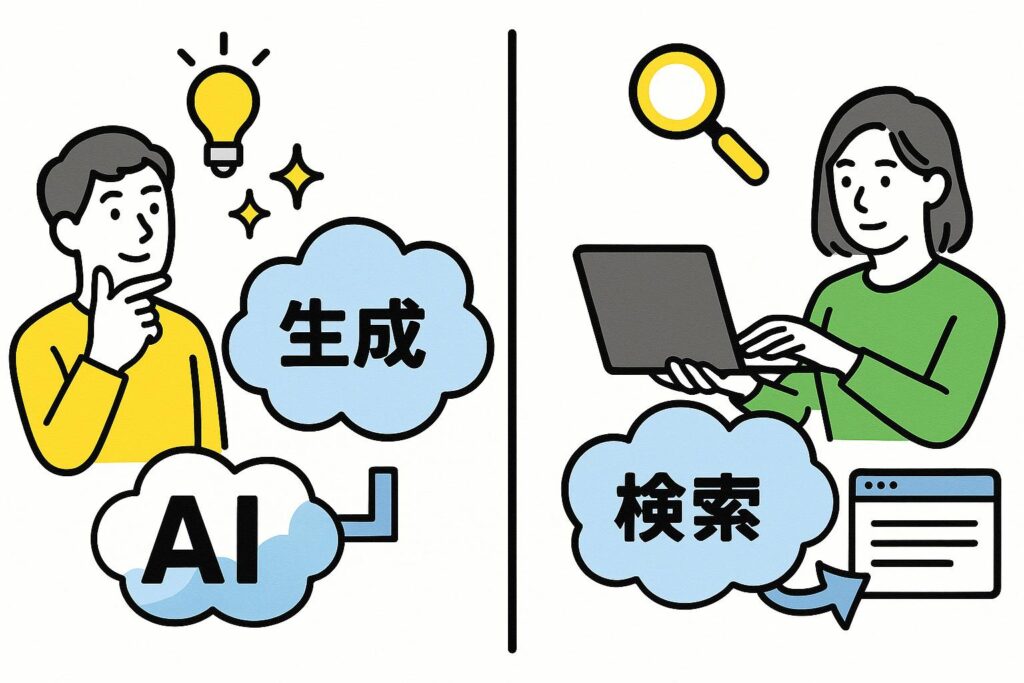
創造性・発想が必要なとき → 生成AI
「文章やアイデアを作る」のに長けており、自然な言語で対話できるのが大きな利点です。
たとえば、ブログ記事の草案、ネーミング案、プレゼン概要、営業メール文章の下書きなどが相性が良いです。
注意点としては、どの情報に基づくか不明な場合があるため、ファクトチェックが重要です。
最新情報・調査が必要なとき → 検索AI
Web上の最新情報をリアルタイムに検索し、根拠となるリンク付きで提示してくれるのが最大の強みです 。
たとえば、競合や市場の最新事情、株価・ニュース基礎情報の背景確認など調査がラクになります。
注意点としては、AIによる検索の信頼性は高めではあるが、それでも誤りの可能性があるので確認は必要です。
AIを「使う側」になる時代
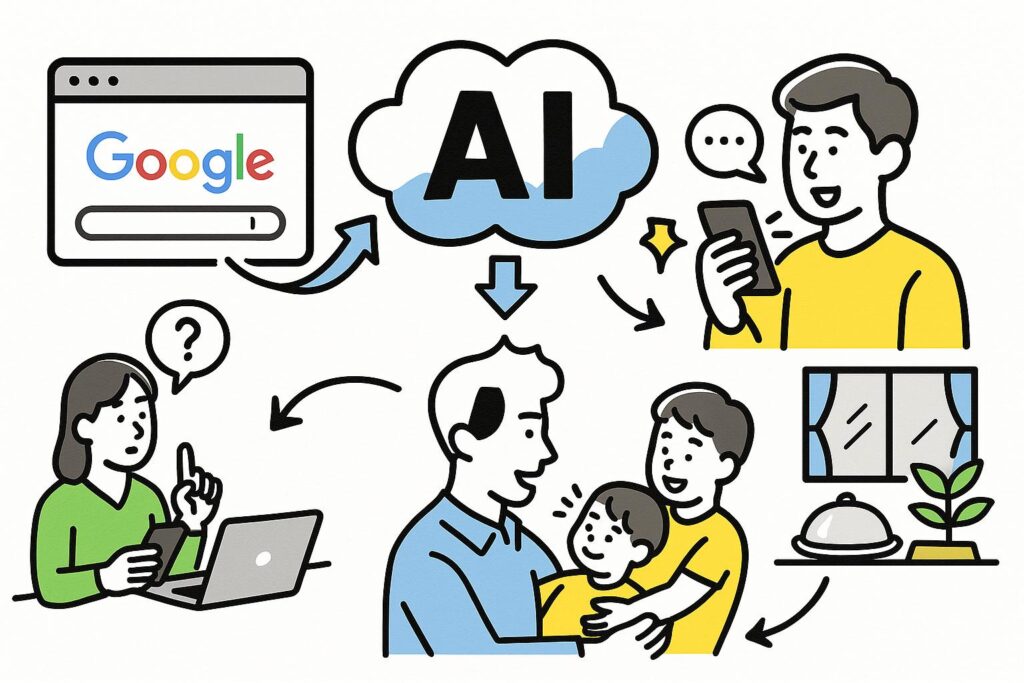
今後、私たちはGoogle検索をしなくなるかもしれません。だからこそ、AIとの付き合い方を今のうちから身につけておくべきだろうと思われます。
なぜなら、情報を探す手段が「Google検索」から「AI検索」へと急速にシフトしているからです。
これは一時的なブームではなく、社会全体のインフラがAI活用を前提とする設計に変わりつつあるからです。これには、どれだけ拒んでもその流れに抗うのは困難になっていくでしょう。
たとえば最近では、「子どもの誕生日におすすめのレストラン」や「2泊3日で楽しめる温泉旅行プラン」など、これまでならGoogleで何時間もかけて調べていたことが、perplexityやFeloに聞くだけで一瞬で具体的な提案として返ってくるようになりました。
「自分から検索する」よりも「話しかける」ことのほうが自然で速いと感じる瞬間がとても増えています。だからこそ、「AIをどう使うか?」を自分事として受け入れて、日々の生活の中で、手で触れて、慣れて、活かしていくことが、これからの「当たり前」になっていきます。
GoogleもAIを使って進化中
GoogleもSGEという新しい仕組みを試しています。「SGE(Search Generative Experience)」は、質問の意味をちゃんと理解して、答えをわかりやすくまとめてくれる仕組みです。
たとえば「社内コミュニケーションツールの選び方」と調べると、ポイントを整理して答えてくれるので、時間をかけて記事を読み比べなくても良くなってきています。
最近では、Google検索したときの上部に要約が表示されるようになりました。まさにこれを指しています。
まとめ
これからの時代、情報収集は「検索する」から「AIに尋ねる」へと変わっていきます。生成AIや検索AIは、それぞれに強みがあります。目的に応じて使い分け、日常の中で慣れていくことが大事です。
AIを“使う側”にまわる意識が、これからの情報リテラシー向上に繋がるでしょう。





